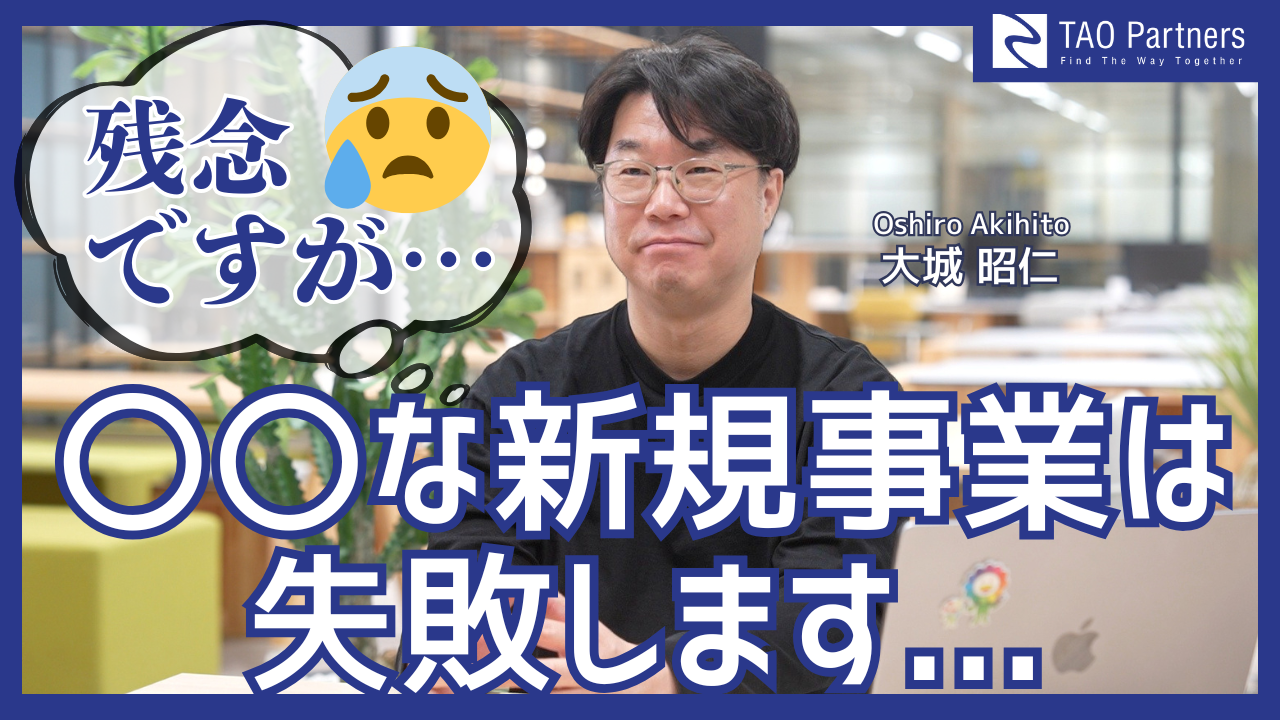| 新規事業開発では、視察やマーケット調査だけでは成功しません。カギとなるのは「はまる」人材の選定です。なぜ人選が最重要なのか、成功する人材の特徴とは?そのヒントをご紹介します。 |
視察やマーケット調査では不十分
総合商社や素材メーカーなどのお客さまから、イノベーションや新規事業開発に関する研修の依頼をよくいただくのですが、話を伺っていると新規事業開発に対する致命的な誤解があるように思います。それはマーケットをよく見さえすれば事業が生まれるという誤解です。この誤解から、2パターンの“お疲れプロジェクト”があちこちで大量生産されています。
パターン①お疲れ視察
「世界最先端のエコシステムを体感しに深圳へ!」で、自動運転ロボット配送を見学し、無人タクシーやスマートシティプロジェクトを体験。生成AIスタートアップにも顔を出してみる。「深圳、やっぱりすごいね!」でも、それからどう動けばいいかわからず、報告書を書いて終わり。
パターン②お疲れマーケット調査
新規事業担当に抜擢され、「成長著しい中国市場でビジネスチャンスを探せ」というミッションが下る。コンサルティング会社からもらった資料を見ると、EV市場は日本の何倍も成長しているし、生成AI・バイオ医療の需要も拡大中。「これはチャンスだ!」と日本側に商品開発を依頼するが、リスクを懸念してなかなか動かない。結果、タイミングを逃してプロジェクトは自然消滅。
20年以上、さまざまな事業開発プロジェクトをやってきた経験から言い切ります。新規事業のカギは、「人選」です。何をするか?と同じくらい、いやそれ以上に、誰がやるかが重要です。そして、「はまる」人選が大事です。「はまる」には2つの意味があります。
「はまる」不良社員を選ぶ
まず、新規事業担当として「はまる」人材をアサインすること。「はまる」人物というのは、リスクを好み、アイディアや着眼に優れ、柔軟で、先の見えない課題に対して、何度も仮説検証を繰り返し、断られても失敗しても粘るタフさを持った人物です。ところが、一方で、通常の業務の中で出世するタイプの人材というのは、段取りがしっかりしていて、決められたことを計画的にきちんとできる、問題解決能力やコミュニケーション能力に優れ、リスクを避け、自分や部下の目標達成を成し遂げられる人材です。つまり、出世しているような人に新規事業をさせても、はまらない。ここに、新規事業人材の人選の難しさがあります。
私はよく、新規事業には「不良社員」をあてて下さいと言っています。新規事業に「はまる」人材は、たいていの場合、現場で有能だと言われながらも、詰めが甘く、ピカピカの出世頭としては扱われていない場合が多いので、そういう何か足りない、有能なのに伸びきらないという人物を現場から選んでもらい、我々の方で専門的なアセスメントをかけて人選します。そうすると、新規事業開発にぴったり「はまる」人材が、時々見つかります。
「はまる」状態=フロー
もう1つの「はまる」は、新規事業開発の活動に「はまる」ことです。人間は、極度の集中状態に入ると、時間感覚が喪失し、自己と周りの環境が一体となるような感覚になる時があります。このような状態を、シカゴ大学のチクセントミハイ教授は、「フロー」状態と名づけました。同教授は、例えばロッククライミングという行為は何の外発的報酬もなく、観客の喝采すら浴びないのに命を賭けてまでのめり込む人がいるのはなぜか、といった疑問を持ったことからさまざまな調査を行い、そうした状態に共通する特徴を抽出していきました。
新規事業は、上記のような「はまる」人材が、フロー状態に「はまる」ことで生まれます。新規事業を経験した人は良く言いますが、プロジェクトを進める過程で、目にするもの、会う人の話が、不思議なくらいに自分の考える事業にどんどん繋がってくる時があります。これがフローです。私自身、何度もこれを経験していますし、新規事業開発プロジェクトの中で、人がこの状態に「はまる」ところを見てきました。新規事業を切り拓く突破力というのは、こういうところから生まれます。
一方、うまく行かないのは、新規事業に対して、お金や評価などをインセンティブにすることです。新規事業に向くタイプの方々にとって最高の報酬は、その仕事そのものになりますし、逆に言えば、お金や評価目当て、その程度のはまり方では、新規事業開発という、最高難度の仕事を成し遂げられる突破力は生まれてこないとも言えます。
最後に、フロー状態はどうやったら出来るのか?チクセントミハイ教授は以下の7つが条件と言っています。
– 目標の明確さ
– どれくらいうまくいっているかの認識
– 挑戦と能力の釣り合い
– 行為と意識の融合
– 注意の散漫を避ける
– 自己、時間、周囲の状況を忘れること
– 自己目的的な経験としての創造性
人選という観点、そして、その人たちが「はまる」環境という観点から、もう一度、新規事業開発のやり方を考え直してみてはいかがでしょうか?より良い方法が見つかるかもしれません。